こんにちは!
今日は「松屋の内的参照価値を逆手に取った戦略」について話していきたいと思います。
内的参照価値というのは「自分の中にある価格の物差し」のこと。
たとえば、牛丼だったら「並盛で500円前後かな」ってなんとなく頭にありますよね。
でも、あまり食べ慣れていない料理だと、「いくらが妥当か」がよく分からない。
それを逆手に取ったのが、今回の松屋の戦略だと思うんです。
最近の松屋って、「シュクメルリ鍋」や「マッサマンカレー」「ビーフストロガノフ」など、ちょっと聞き慣れない“世界の料理”を定期的に出していますよね。
正直、僕も最初「シュクメルリ?何それ?」となりましたが、「聞いたことない=食べてみたい」という心理が働いて、つい頼んでしまいました。
しかもその価格、800円〜900円台だったりします。
いつもの牛めしが400円台なのに対して、その2倍近い価格でも「まあこんなもんか」と思えてしまうのは、まさに内的参照価値が定まっていないからなんですよね。
この感覚、タピオカブームのときにも似たような現象がありました。
中国では一杯100円〜200円程度で飲めるタピオカが、日本に入ってきたとたん、600円くらいで売られるようになったという話。
でも、その値段でもみんな普通に買っていましたよね。
なぜかというと、「タピオカの相場を知らないから」。
つまり、“高いのか安いのか”が判断できない状態だったわけです。
ここにも内的参照価値の空白地帯があったということですね。
松屋の面白いところは、この「価格の物差しがない領域」に、あえて挑戦している点です。
あくまで“牛丼屋”の枠組みは保ちつつも、世界の料理を取り入れることで、「価格の感覚をずらす」ことに成功している。
しかも、ただ高く売るだけじゃなく、「松屋だからこそ気軽にトライできる」という安心感もあるので、ユーザーにとっては、ハードルが下がるんですよね。
この「価格の物差しを持たれていないゾーンに入っていく」やり方は、飲食に限らず、あらゆる業界で応用できるヒントだなと思いました。
松屋の取り組みの裏には、そんな戦略的な意図が垣間見えて、かなり面白いですよね^^
それでは、本日は以上です!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
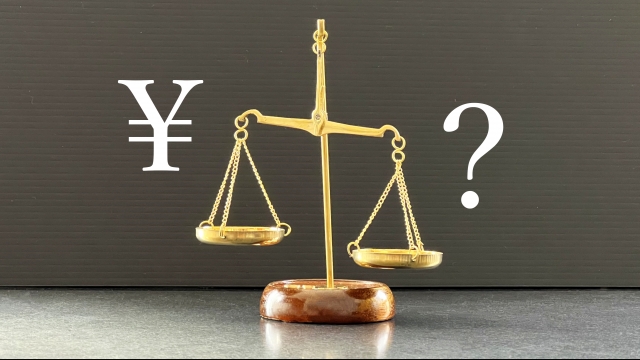











コメント